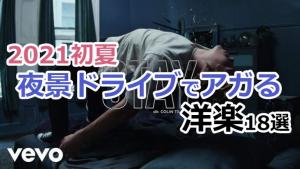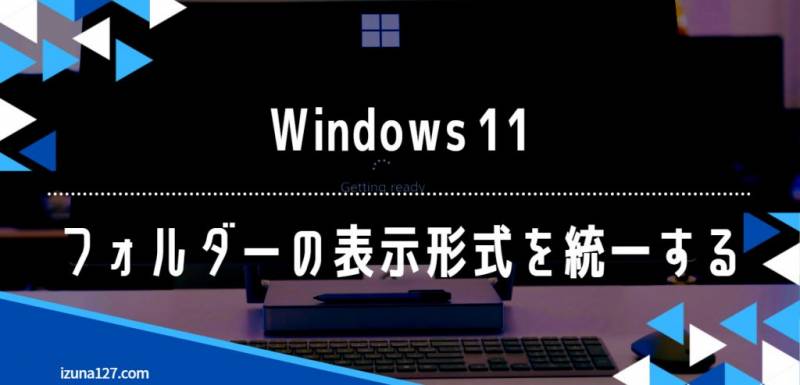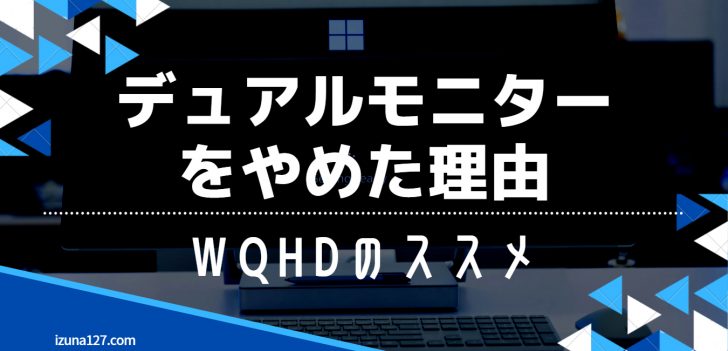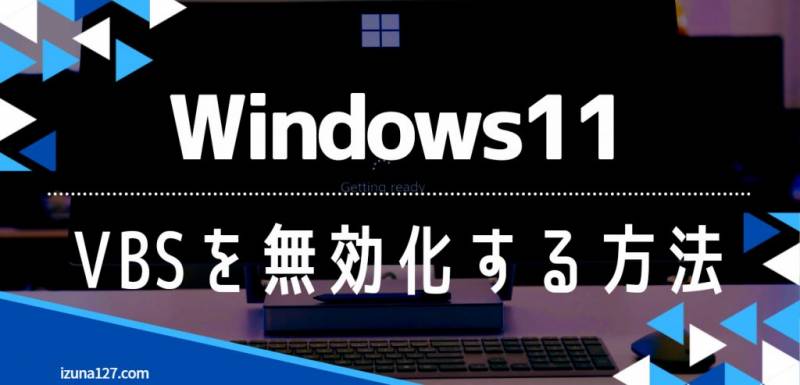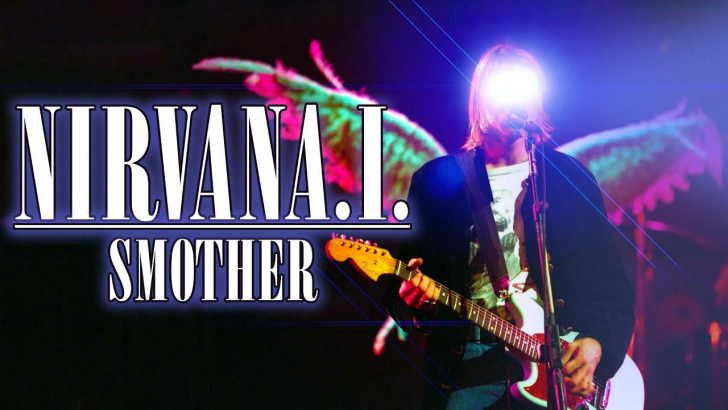これはAI(人工知能)が作ったNirvana(っぽい)新曲。
「あーそれっぽい。このフックはあのアルバムの曲っぽいな。わかるわー・・・」
べつに嫌味ではなくて、音楽に限らず創作に携わる者なら「模倣」からアイデアを得ることは少なくないと思う。そのプロセスをメチャメチャ効率化して凝縮して研ぎ澄ますと、こんなのが出来上がるんだと感心した次第。
オリジナリティとは?
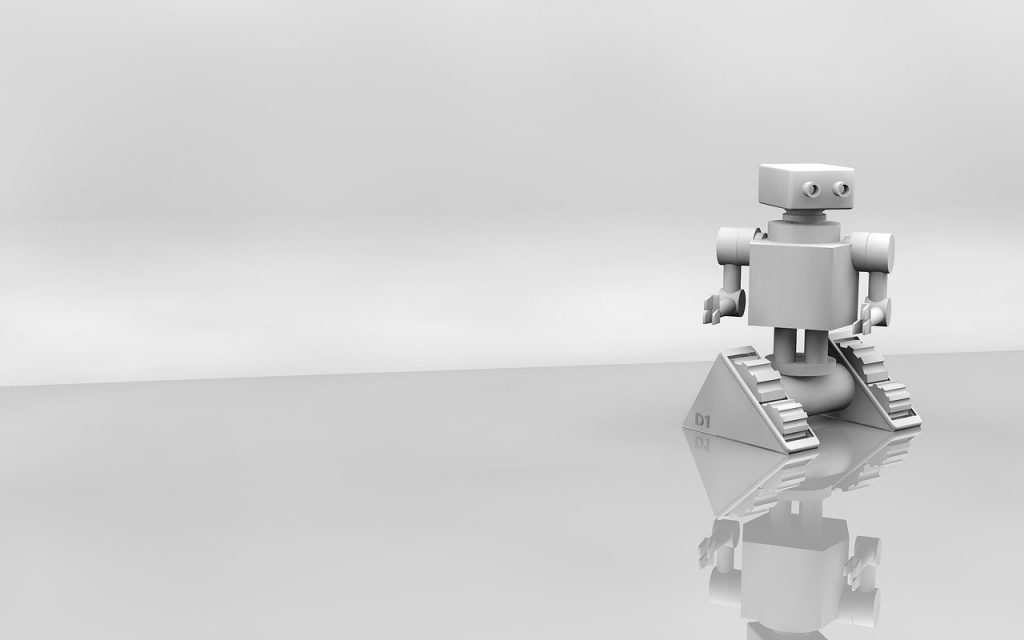
誰かの「モノマネ」を機械にひたすら学習させ続けると、機械はその美味しい部分を凝縮した究極のモノマネを見せてくれるかもしれない。だけどそれは模倣でしかなく、蓄積されたデータの山から再構築された幻に過ぎない。
対してAIは、そこから一歩踏み込んでオリジナル(のようなもの)を生み出す域に到達したという事なのか・・・?
その制作プロセス
アーティストの楽曲をセクションごと、パートごとに分解したものを20~30曲分用意してAIに聞かせる。これはおそらく楽曲をMIDIに落とし込んで、それをバース・コーラス・間奏、ギターやベースやドラムスなどバラバラに分解してデータベース化したものだろう。
AIはそれをベースに5分ほどのリフを作り出すが、その90%は使い物にならないらしい。そこから使えるフレーズを人間が選別して、さらに学習させるというプロセスをひたすら繰り返す。
歌詞もしかり、専用のAIがデータベースをもとにそのアーティストが好んで使う語句や傾向を把握して選別する。

最終的に生み出される曲は、ボーカルパート以外すべてAIによる演奏。歌唱技術だけはまだ人知を超えられないっぽい。
聴いて思うのは演奏の癖やリアルさまで上手く再現されてるなと感心する。学習前の素材を用意する段階で、かなり精度の高いデータを抽出していると思われる。
ギターひとつ取っても6つの弦をパラで収録し、奏法含めてデータに落とし込まないと再現が難しいであろう箇所がある。それはすなわちコピーした演者の技量や主観も多少は含まれることになるのだけれど。
最終的な微調整やミキシングなどのエンジニアリングは人の手によるものだろう。
AIが生み出したのは事実なんだろうけど、要所のジャッジに人間の主観が入ってる時点で「それどうなの?」と思わなくもない・・・。
元も子もない話だけど、アーティストはわざわざ「過去の自分に似せた曲を作ろう」と思いながら創作したりはしない。結果として生み出されたモノに「らしさ」や「既視感」が含まれていたとしても、それは「模倣」をベースにしたものとは根本的に違う。
本質までは模倣できない

ひとりの人間が誕生してから作品を生み出すまでに費やされた時間や経験、快楽や苦悩は、表面をなぞるだけで得られるものからは程遠い。
AIがカート・コバーンやジミヘンに代わってメロディを紡ぎ出すのは難しい。
それは本人しか成し得ないのだから。